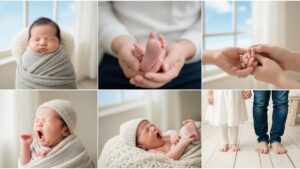軽くて高性能なのでママも楽々!
新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー
1歳前後の子どもがつま先で歩く様子を見て、不安になる親御さんは多いです。ここでは「わざと」かどうかの見極め方から、身体的な原因、発達行動としての背景、家庭での対応、受診時の準備までを具体的に説明します。観察ポイントや簡単チェックリストも載せていますので、日常で使いやすい形で確認しやすくまとめました。落ち着いて見守り、必要な場合は適切に相談できるよう参考にしてください。
つま先で歩くのは1歳の子がわざとすることがある?

つま先で歩く動作は、遊びや真似の一環として意図的に行うことがあります。特に感覚的に楽しいと感じたり、キャラクターの真似をしている場合は「わざと」行っている可能性が高いです。1歳前後は歩行が安定していないため、つま先歩きが目立つことも珍しくありません。
ただし、繰り返し長時間にわたってつま先歩きが続く場合は、身体的な要因や感覚の違いが関係していることもあります。まずは観察をして、頻度や状況、左右差、痛そうにしていないかなどを確認しましょう。次のセクションで具体的な観察ポイントを挙げます。
観察ポイント
つま先歩きが見られたときは、まず以下をチェックしてください。
- いつ、どの場面で起きるか(遊び中、移動時、疲れている時など)
- 左右どちらかに偏っているか
- 疼痛や不快を示す様子があるか(泣く、足を触らせたがらないなど)
- 歩行の頻度と持続時間(短時間の真似か、終日続くか)
これらをメモに残すと受診時に役立ちます。特に「特定の靴や裸足で変わるか」「階段や段差でどう動くか」など、日常の具体的な場面を観察すると原因のヒントになります。周囲の大人が「やめて」と伝えたときの反応も確認しましょう。やめられる場合は意図的な側面が強く、やめられない場合は身体の問題や感覚の違いが示唆されます。
いつから始まったか
つま先歩きがいつ始まったかを把握することは重要です。歩き始め直後に見られる一時的なものであれば、発達の一過程として様子を見る場合が多くなります。初めて見た時期、頻度が増えた時期、他の発達の節目(つかまり立ち、独歩)との関連も記録してください。
もし生後すぐや乳児期から継続している場合や、徐々に悪化している場合は別の理由が考えられます。成長とともに自然に改善するケースもありますが、6か月以上継続する、左右差がある、運動の他の側面に遅れが見られる場合は専門家に相談する目安になります。
周囲の反応の見方
家族や保育者の反応は子どもの行動に影響します。興味を引く反応(褒める、注目を向ける)は行動を強化することがあります。逆に叱ると意図的な行動はやめる場合がありますが、身体的理由なら叱っても改善しません。
保育園での様子や他の子どもとの違いも参考になります。保育士が気づいているか、園での記録を確認しましょう。周囲が一貫した対応を取ることで、意図的な行動は減る傾向があります。感覚の問題がある場合は、大人が注意しても反応が変わらないため、その点も見分ける材料になります。
日常で確認する簡単チェック
家庭で簡単にできるチェック項目を紹介します。
- 裸足と靴を履いた時で歩き方が変わるか
- おもちゃで注意をそらしたときにつま先歩きが減るか
- 眠い・疲れているときに増えるか
- つまずきや転倒が多いか
これらを1〜2週間記録すると傾向が見えます。チェックは短時間でよいので、毎日の生活の中で観察を続けてください。明らかに改善が見られない場合や不安が強い場合は、次のステップとして医療機関に相談することを検討しましょう。
キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!
赤ちゃんとのお出かけが快適に♪
つま先歩きが起きる身体的な理由

つま先歩きには筋肉や骨の発達、神経系の状態など身体的要因が関わることがあります。筋肉の緊張状態や足部の構造的な特徴が歩行パターンに影響を与えるため、観察と必要な評価が重要です。
筋緊張が高いとふくらはぎやアキレス腱が短縮し、かかとを着かずにつま先で歩くことがあります。これは脳性まひなどの神経系の問題だけでなく、一時的な筋緊張のアンバランスでも起こりえます。日常で筋緊張の高さを示す他のサイン(抱っこで足を伸ばしにくい、寝返りがぎこちないなど)も注意して見てください。
また、足の骨格や筋肉の発育により、足底のアーチや足首の柔軟性が影響することがあります。扁平足や足関節の可動域制限があると、かかと接地が難しくなり、つま先歩きにつながる場合があります。痛みや不快を避けるためにつま先で歩くこともあるため、足を触ると嫌がる、歩行時に泣くといった症状があれば注意が必要です。
重篤な兆候としては左右差の著しい歩き方、筋力低下や他の運動発達の遅れがある場合です。このような場合は小児整形外科や発達外来での診察・評価を早めに受けることをお勧めします。専門家は視診、触診、必要に応じて画像検査や神経学的評価を行い、治療方針を決定します。
筋緊張の影響
筋緊張のバランスが崩れると歩行パターンに変化が出ます。特に下肢の伸筋群や屈筋群の緊張差があると、かかとが着きにくくなり、つま先での接地が起こります。筋緊張が高い場合はふくらはぎの硬さやアキレス腱の短縮が見られることが多いです。
筋緊張は成長とともに変わるため、一過性の高緊張であれば自然改善することもありますが、継続する場合は理学療法やストレッチ指導が有効です。家庭でできるストレッチや遊びを通した筋のほぐし方を療法士から教わると効果的です。
足の構造や発育
足底アーチの形成や足首の可動域は年齢とともに変わります。扁平足や足関節の過可動あるいは制限がつま先歩きの背景になることがあります。靴のサイズや形が合っていない場合も歩行に影響することがあるため、履物の確認も忘れないでください。
足の形や関節の状態が気になる場合は、整形外科で立位や歩行時の観察、必要な画像検査を受けると安心です。
痛みや違和感の可能性
痛みを避けるためにつま先で歩く場合があります。足裏やかかと、つま先部分に痛みがあると、自然と着地方法が変わります。歩行時に泣く、足を触られるのを極端に嫌がる、歩行量が減るといったサインがあれば痛みを疑ってください。
痛みが原因であれば、原因部位の治療や安静、適切な靴の使用で改善することが多いです。症状が強ければ早めに医療機関で診てもらいましょう。
小児整形外科での診察目安
以下の場合は整形外科受診を検討してください。
- 6か月以上続くつま先歩き
- 明らかな左右差や片側のみの多さ
- 歩行以外の運動発達の遅れがある場合
- 痛みや歩行困難がある場合
受診では歩行観察、関節可動域の測定、神経学的な評価が行われ、必要に応じてレントゲンやその他検査が行われます。適切な介入を受けることで改善が期待できます。
つま先歩きが発達行動として出る場合

発達過程でつま先歩きが現れることがあります。子どもは身体感覚を探りながら学ぶため、つま先歩きが一定期間観察されることは珍しくありません。ここでは自発的な行動や感覚の違い、発達障害との関連の見方について説明します。
遊びや真似としてのつま先歩きは、周囲の人やキャラクターの動きを模倣することから始まる場合があります。意図的に行っていると判断できれば、注意をそらす工夫や代替行動を教えることで改善することが多いです。
感覚処理の違いがあると、特定の足裏の感覚を好んだり嫌ったりしてつま先歩きが現れることがあります。感覚過敏で足底の刺激を嫌う場合や、鈍麻でしっかりと地面を感じにくいためつま先で歩く場合などが考えられます。これらは発達の個人差内にあることも多く、専門家による評価が助けになります。
自発的な遊びや真似
子どもは新しい動きを試すのが好きで、つま先歩きも遊びの一部として取り入れられることがあります。親や保育者が反応することで行動が強化されることがあるため、注意の向け方を工夫すると自然に減ることがあります。
代替行動としてかかとを意識する遊びやバランス系の遊びを取り入れると、楽しく自然に改善できます。無理にやめさせるのではなく、好奇心を利用してトレーニングするアプローチが有効です。
感覚の違い(感覚過敏・鈍麻)
感覚過敏の子は床の感触を嫌ってつま先で接地することがあります。一方で感覚鈍麻の子は足底の感覚を十分に感じられないため、つま先での接地を選ぶこともあります。どちらの場合も保護者の観察で「どのような刺激で行動が変わるか」を記録すると専門家の評価に役立ちます。
感覚面のサポートは、刺激の調整や感覚統合を意識した遊びが中心になります。作業療法士による評価と指導が効果的です。
ASD(自閉スペクトラム症)との関連の見方
ASDの一部の子どもでは、特徴的な運動パターンや感覚の偏りとしてつま先歩きが見られることがあります。ただし、つま先歩きだけでASDと結びつけることはできません。社会的なやり取り、言葉の発達、興味の偏りなど他の発達特徴があるかどうかを総合的に評価する必要があります。
つま先歩きに加えて社会性やコミュニケーションに心配がある場合は、発達外来や保健センターで早めに相談するとよいでしょう。
ADHDや発達の個人差との区別
ADHDやその他の発達の個人差では、落ち着きのなさや運動の粗さが影響してつま先歩きが見られることがあります。しかしこちらも単独の症状で診断することはできません。全体の発達の流れや日常生活での困り感を踏まえて、必要なら専門家の評価を受けてください。
家庭での観察記録が受診時の重要な情報になります。行動の頻度や状況を具体的に伝えられると診断がスムーズになります。
家庭でできる対応と観察方法

家庭での日常観察と簡単な対応は早期発見と改善につながります。無理にやめさせるのではなく、遊びの中で自然にかかとを使う練習を取り入れると効果的です。ここでは声かけや遊び、受診の目安、園との連携方法を紹介します。
日々の観察は短時間で構いませんが、タイミング(朝、午後、疲れている時など)や環境(裸足、靴)ごとに記録しておくと変化が分かりやすくなります。成長とともに改善するケースも多いため、焦らずに見守る姿勢が大切です。
日常での声かけと記録の取り方
声かけは否定的にならないように配慮しましょう。「かかとをつけて歩いてみようね」と促す程度で十分です。歩行の様子をスマホで短時間録画しておくと、医師や療育者に見せられて便利です。
記録は以下のように簡潔に残すとよいです。
- 日付・時間帯
- 裸足/靴の有無
- 行動の場面(遊び中、移動中)
- 継続時間や頻度
- その他の症状(痛がる、疲れやすい)
遊びや運動でのサポート例
遊びを通したサポートは効果的です。例としては以下があります。
- かかとを意識するゲーム(床に「かかとスタンプ」を作る)
- バランス遊び(ライン歩きや平均台)
- 足首やふくらはぎを優しく伸ばすストレッチを遊びに取り入れる
遊びのなかで褒めて成功体験を積ませると、子どもが意識的にかかとを使う習慣がつきやすくなります。
受診や相談を検討するタイミング
次の場合は早めに専門家に相談してください。
- 6か月以上変化がない
- 片側だけ強い、左右差がある
- 歩行以外の発達に不安がある
- 痛みや歩行困難がある
まずは小児科で相談し、必要に応じて整形外科や発達外来に紹介してもらうとよいでしょう。
保育園・療育との連携ポイント
保育園や療育施設と情報を共有すると家庭だけでの対応に限界がある場合に助かります。観察記録や短い動画を園に見せ、日常での様子や対応を統一してもらいましょう。園のスタッフからのフィードバックも家庭での対応に活かせます。
医療機関・専門家に聞くときの準備
受診時に伝える情報を整理しておくと診察がスムーズです。日常の観察記録、動画、必要な既往歴や家族歴をまとめておきましょう。これにより診断の精度が上がり、適切なフォローが受けられます。
診察前にチェックリストを作り、医師や療法士に具体的に見せられるように準備してください。次に伝えるべき情報や受診先の選び方、よく行われる検査について説明します。
相談時に伝えるべき情報
受診時には以下を伝えると役に立ちます。
- いつから始まったか(初見時期)
- 頻度と持続時間
- 裸足と靴での違い
- 左右差やその他の体の症状
- 家族歴(神経・整形の既往など)
- 日常での困りごとや園からの指摘
短い動画や簡潔なメモを持参すると、言葉だけで説明するより具体的に伝えられます。
受診先(小児科・整形外科・発達外来)の選び方
まずはかかりつけの小児科で相談するのが一般的です。小児科医が必要に応じて整形外科や発達外来に紹介します。歩行の不安が主であれば小児整形外科、発達の他の面も心配であれば発達外来や児童精神科、作業療法士のいる施設が適しています。
紹介状や記録を持参すると初診がスムーズになります。
検査や診断でよく行われること
診察では視診と触診、歩行観察が中心です。必要に応じて以下が行われることがあります。
- 関節可動域の測定
- 筋緊張や筋力の評価
- レントゲンなどの画像検査
- 発達評価(質問票や発達検査)
- 動画解析や歩行分析(専門施設)
検査結果に応じて理学療法、作業療法、装具療法や外科的治療の検討が行われます。
受診後のフォロー体制の確認
受診後は治療計画やリハビリの頻度、経過観察のスケジュールを確認しましょう。家庭での具体的な練習方法や保育園での配慮事項を文書でもらえると実践しやすくなります。必要ならば多職種での連携(小児科、整形外科、理学療法士、作業療法士)を依頼してください。
まとめ:つま先 歩き 1歳 わざと をどう考えるか
1歳前後のつま先歩きは、遊びや真似として意図的に行うこともあれば、筋緊張や足の構造、感覚の違いが原因で起きることもあります。まずは頻度や場面、左右差、痛みの有無を日常で観察し、簡単な記録と短い動画を残しておくことが重要です。
多くは成長とともに改善しますが、6か月以上続く、左右差が目立つ、他の発達面に不安がある、痛みがある場合は早めに医療機関で相談してください。家庭では遊びを通じたサポートや保育園との連携で自然な改善を促せます。専門家と連携しながら無理なく子どもの歩行を支えていきましょう。
充実の100ピースブロック!
アメリカと共同開発された人気の知育玩具


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)