軽くて高性能なのでママも楽々!
新生児から3歳まで長く使えるおすすめベビーカー
育児の初期にかかるオムツ代やミルク代は家計に影響するため、月ごとの目安と節約法を知っておくと安心です。
オムツ代とミルク代は月にいくらかかるの?
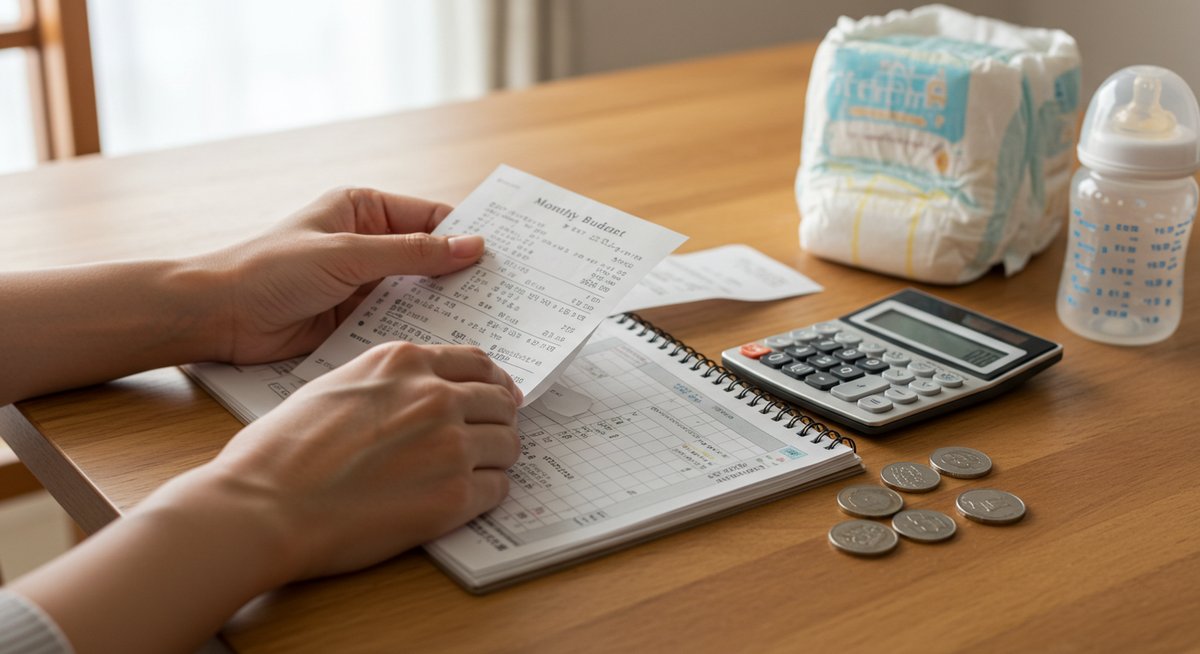
赤ちゃんの成長に合わせてオムツとミルクの必要量は変わります。ここでは新生児期から1歳前後までを想定し、月ごとの目安と節約ポイントを紹介します。
新生児期の目安
新生児期(生後0〜1ヶ月)はオムツの消費が最多で、1日に8〜12枚程度が目安です。高品質のプレミアムタイプを使う場合は単価が高めになりますが、肌トラブルを避ける観点で検討する家庭も多いです。
ミルクは母乳が十分でない場合、粉ミルクを使う量が増えます。混合育児や完全粉ミルクの場合、1ヶ月で0.8〜1.2kgの粉ミルクを使う家庭が多く、月間コストは銘柄や購入方法で変わります。母乳育児なら粉ミルクのコストは抑えられますが、哺乳瓶の消耗や洗浄剤などの費用は発生します。
0〜6ヶ月の平均額
0〜6ヶ月の期間は体重の増加に伴いミルクの必要量が徐々に増え、オムツも引き続き多く消費します。一般的な目安として、オムツ代は月5,000〜10,000円、ミルク代は粉ミルク中心で月5,000〜15,000円程度が多いです。これは使うブランドや購入経路、母乳との併用比率によって幅があります。
費用の変動要因としては、まとめ買いや定期購入の割引、ドラッグストアのポイント利用などがあり、上手に活用すると負担がかなり軽くなります。哺乳関連の小物(哺乳瓶、乳首、消毒用品)も短期的にまとまった出費になりますので、初期費用として予算に入れておくと安心です。
6〜12ヶ月の平均額
6〜12ヶ月になると離乳食が始まり、ミルクの消費量は徐々に減少します。オムツサイズは上がるため1枚あたりの単価は上がることがありますが、枚数自体は減る傾向です。月ごとの目安はオムツ代が4,000〜8,000円、ミルク代が3,000〜8,000円程度が一般的です。
離乳食の食材費や食器、ベビーフードを使う場合の追加費用も発生します。外出が増えると携帯用おむつやおしりふきの消費が増える場合もあるため、ライフスタイルに合わせて変動します。まとめ買いやブランドの見直しで負担を抑えられます。
計算に使うポイント
月額を計算する際は、以下のポイントを押さえてください。
- オムツの枚数(1日あたりの枚数×30日)
- オムツの単価(セール価格や定期便の割引を考慮)
- 粉ミルクの消費量(1回分の粉量×1日回数×日数)
- その他消耗品(おしりふき、哺乳瓶関連、消毒用品)
これらを組み合わせて試算すると現実的な月額が出ます。変動がある項目は余裕を持って見積もると家計管理がしやすくなります。
キッズデザイン賞を受賞した折り畳みベッド!
赤ちゃんとのお出かけが快適に♪
月ごとのオムツ代の内訳と節約法

オムツ代はサイズや使用枚数、購入方法で大きく変わります。ここでは月ごとの内訳と具体的な節約法を説明します。
サイズ別消費量の目安
サイズ別の1日あたり消費量の目安は以下の通りです。
- S・新生児:8〜12枚
- M(3〜6ヶ月前後):6〜9枚
- L(9ヶ月前後〜):5〜8枚
成長に伴い枚数は減りますが、替え時点や夜間の替え方で差が出ます。夜用を別に用意すると夜間の交換回数を減らせますが、単価はやや高めです。
購入方法で変わる単価
オムツの単価は購入方法で差が出ます。主な購入方法と特徴は以下の通りです。
- ドラッグストア:セール時に安く買える。ポイント還元あり
- ネット通販:まとめ買いで割引、定期便で安定
- 量販店:大容量パックで単価が下がる
まずは複数のルートを比べ、セール情報や定期便の割引をチェックするとよいでしょう。
セール・クーポンの活用法
セールやクーポンは月間コストを下げる大きな手段です。具体例としては、
- 定期セール(ドラッグストアの週末セール)
- メーカー直販の初回割引やポイント還元
- クレジットカードや電子マネーの還元
賢く使うためには価格を比較する習慣と、ストックできるスペースの確保が必要です。
布おむつを選ぶ場合の費用感
布おむつは初期投資が必要ですが、長期的に見るとコスト削減につながる場合があります。主な費用項目は以下です。
- 初期購入(布おむつ本体、カバー):数万円程度
- 洗濯にかかる水道光熱費:増加分を見積もる
- 洗剤や収納用品:少額の消耗品
布おむつは手間がかかりますが、ゴミ処理の負担軽減や単価削減につながりやすい点がメリットです。
ミルク代の種類別費用と節約術

粉ミルクのブランドや調乳方法で費用は変わります。ここでは種類別の費用感と節約術をまとめます。
粉ミルク完母・混合での差
完全母乳(完母)の場合、粉ミルク費用はほぼかかりませんが、補助的に粉ミルクを用意する家庭もあります。混合育児の場合、粉ミルクの使用量が中程度で、完全粉ミルクでは最も費用がかかります。目安として完全粉ミルクは月5,000〜15,000円、混合はその半分程度のことが多いです。
どの方法でも哺乳瓶や消毒用品の初期費用は発生するため、初月は通常より高く見積もってください。
調乳・保存にかかる消耗品費
調乳に関わる消耗品としては以下が挙げられます。
- 哺乳瓶、乳首の交換(定期的な交換が必要)
- ミルクスプーン、計量器
- 消毒グッズ(煮沸、電子レンジ用ケース、消毒液)
- 保存用の哺乳瓶容器や冷蔵保存袋
これらは長期的な消耗品ですが、まとめ買いで単価を下げられる場合があります。
安く買うための買い方
粉ミルクを安く買うコツは次の通りです。
- まとめ買い・業務用サイズを検討する
- 定期購入で割引を受ける
- ネット通販のクーポンやポイントを利用する
- 価格比較サイトや価格履歴をチェックする
ただし、賞味期限や保管スペースも考慮して購入量を決めてください。
ミルク代を抑える注意点
価格だけで選ぶと品質や赤ちゃんの消化適性に合わない場合があります。安さ重視で急にブランドを変えると赤ちゃんの下痢やアレルギー反応が出ることがあるため、切り替えは慎重に行ってください。
家計への影響と予算の立て方

オムツ代とミルク代は継続的な支出です。家計に与える影響を把握し、現実的な予算を立てることが重要です。
月間予算の組み方
月間予算を作る際は固定費と変動費に分けて考えます。まずは実際のレシートや購入履歴を1〜3ヶ月分集め、平均を出してください。その上で、
- 安全マージン(予備費)を10〜20%入れる
- セール月にまとめ買いするための貯金を毎月少しずつ積み立てる
こうしたルールを作ると急な出費にも対応しやすくなります。
年間コストの見積もり例
年間コストは月額を12倍するだけでなく、成長に伴う変動も考慮します。例としては、
- 0〜6ヶ月:月平均12,000円 → 6ヶ月で72,000円
- 6〜12ヶ月:月平均7,000円 → 6ヶ月で42,000円
合計で年間約114,000円程度が一つの目安になりますが、地域差や選択によって上下します。
収入に合わせた節約プラン
収入が限られている場合は、優先順位をつけて予算配分を行います。例:
- 必要優先:安全で清潔なオムツ、赤ちゃんに合うミルク
- 調整可能:ブランドや購入ルートの見直し、布おむつの導入検討
ボーナスや臨時収入があれば、まとめ買いのストックに回すと月負担を平準化できます。
補助や給付の確認ポイント
自治体や企業の子育て支援、育児用品の助成などが利用できる場合があります。確認しておくポイントは以下です。
- 住んでいる自治体の子育て支援制度
- 企業の福利厚生や補助(育児手当等)
- NPOや地域のフリーマーケットでの支援
制度は地域ごとに異なるため、自治体の窓口や公式サイトで最新情報を確認してください。
おむつ代・ミルク代の実例と比較データ
実際の家庭の例を見ると、選択と生活スタイルによる差がわかりやすくなります。ここでは代表的な実例と比較を紹介します。
共働き家庭の実例
共働き家庭では外出や保育園に合わせた消耗が増えることが多いです。オムツは外出用に小分けパックを用意し、ミルクは持ち運びに便利な調乳ボトルや粉携帯容器を使うため消耗品費がやや高めになります。月平均はオムツ8,000円、ミルク10,000円前後になることがあります。
里帰り出産時の実例
里帰り中は実家のサポートで家計負担が軽くなることがあります。実家の在庫やサポートによってオムツ・ミルクの購入量が抑えられる場合もあり、一時的に月額が下がることが多いです。ただし帰宅後に補充が必要になる点は注意してください。
地域差やライフスタイル別の比較
都市部では物価や消耗品単価が若干高い傾向がありますが、ネット通販の普及で差は縮まっています。ライフスタイル別では外出頻度が高い家庭や外食が多い家庭は携帯用消耗品の消費が増えます。逆に在宅中心で節約意識の高い家庭はストック管理でコストを抑えています。
実例から学ぶ節約のコツ
実例から見えてくる節約のコツは次の通りです。
- 定期購入やまとめ買いで単価を下げる
- セールやポイントを活用して必要分だけ買う
- 必要に応じて布おむつや代替ブランドを試す
- 家族や地域のサポートを活用して一時的な負担を軽減する
これらを組み合わせて、家計の負担を抑えていきましょう。
充実の100ピースブロック!
アメリカと共同開発された人気の知育玩具


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2c6f69.68be57c7.4c2c6f6a.76b5924a/?me_id=1422856&item_id=10000751&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbabuuu%2Fcabinet%2Fkd0902%2Fdefault%2Fs1%2F4972990193764_s1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c28428d.41fa498e.4c28428e.95715918/?me_id=1403613&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneomamaism%2Fcabinet%2F10703320%2Fbed-sam001ldk.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c284da5.67fc155c.4c284da6.f6b1c54b/?me_id=1427150&item_id=10000107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnicoselection%2Fcabinet%2Fimgrc0080121652.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)








